
【学び直し英文法】分詞構文とは
文法構文とは基本的に「~ing」といった現在分詞、「~ed」のような過去分詞が、文中で「接続詞と動詞を兼ねた働きをしている」構文のことを指し、高校英語の最初のうちに習う文法のうちでも躓く人が多い文法です。今回はそんな分詞構文についての基本をおさらいをしていきます。
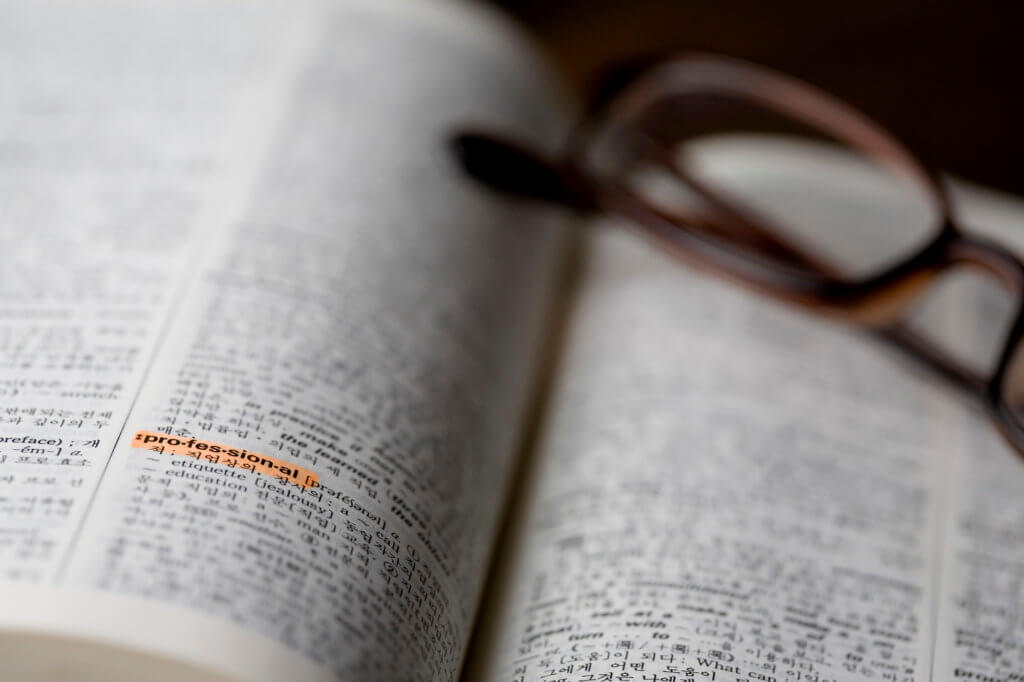
分詞構文とは基本的に「~ing」といった現在分詞、「~ed」のような過去分詞が、文中で「接続詞と動詞を兼ねた働きをしている」構文のことを指し、高校英語の最初のうちに習う文法のうちでも躓く人が多い文法です。
今回はそんな分詞構文についての基本をおさらいをしていきます。
分詞構文の文法
まずここで例文を見てみましょう。
【例文】
When she found that ring, she was very relieved.
その指輪を見つけた時、彼女はとても安心した。
接続詞「when」を使ったごく一般的な表現で、二つのことが同時に起きていることを説明している文章です。
この文章を分詞構文で表現すると、
【例文】
Finding that ring, she was very relieved.
その指輪を見つけて、彼女はとても安心した。
となります。
どちらも全く同じ意味の文章ですが、分詞構文を用いることによって単語の数が少なくなり文章が短くなりました。
分詞構文とは「分詞」を用いた構文で、分詞が「接続詞+動詞」の役割を持ちます。
【例文】
When she found that ring, she was very relieved.
Finding that ring, she was very relieved.
元の文章から接続詞「when」を省略し、動詞「found(findの過去形)」を分詞にします。
そして、そして主語が主節と同一の人・物の場合は主語も省略します。
※文脈上一番伝えたいことは「彼女が安心した」ことなので、この説が文章における「主節」、「指輪が見つかった」ことは付帯する情報なので「従属節」となります。
そうすることで分詞構文を使った文章にすることができます。
分詞構文は文語的でやや固い表現なので、日常会話ではあまり使わない表現です。
分詞構文の5つの意味
分詞構文は文脈によって異なる意味で解釈されます。
意味のパターンごとに分類して、解説をしていきますので理解を深めましょう。
時を表す用法:「~するとき」
接続詞「while」や「when」、「as」によって導かれる節の場合、分詞構文では「~するとき」という意味の働きを持つことがあります。
【例文】
While I waited at the bus stop,I met my mother.
バス停で待っていると、母に会いました。
Waiting at the bus stop, I met my mother.
バス停で待っていると、母に会いました。
条件を表す用法:「~するならば」
接続詞「if」に導かれる節の場合、分詞構文では「もし~すれば」という意味の働きを持つことがあります。
【例文】
If you go ahead for 200 meters,you will get to the bus stop.
200メートルまっすぐ行けば、バス停に着くでしょう。
Going ahead for 200 meters, you will get to the bus stop.
200メートルまっすぐ行けば、バス停に着くでしょう。
譲歩を表す用法:「~するけどれも」
接続詞「although」に導かれる節の場合、分詞構文では「~だが」という意味の働きを持つことがあります。
【例文】
Although I understand your opinion, I do not agree with it.
あなたの意見は理解できますが、私は賛成できません。
Understanding your opinion, I do not agree with it.
あなたの意見は理解できますが、私は賛成できません。
原因・理由を表す用法:「~するので」
接続詞「because」「 since」「 as」に導かれる節で、「~するので」や「~だから」と原因や理由を意味の働きを持つことがあります。
【例文】
Since you are a minor, you should not drink alcohol yet.
未成年なので、まだお酒は飲んではいけません。
Being a minor, you should not drink alcohol yet.
未成年なので、まだお酒は飲んではいけません。
付帯状況を表す用法:「~しながら」・結果を表す用法:「…そして~した」
接続詞「and」で繋ぐ節で、「~しながら」という付帯条件や「…そして~した」という結果の意味の働きを持つことがあります。
【例文】
My mother was humming, and she was cooking dinner.
母は鼻歌を歌いながら、夕食を作っていた。
My mother was humming, cooking dinner.
母は鼻歌を歌いながら、夕食を作っていた。
【例文】
A large tornado hit that city,and it was causing extensive damage.
その街を大きな竜巻が襲い、甚大な被害をもたらした。
A large tornado hit that city, causing extensive damage.
その街を大きな竜巻が襲い、甚大な被害をもたらした。
分詞構文の位置
分詞構文は文中のどの位置において使うのが正しいのでしょうか?
分詞構文の置く位置のパターンについて解説していきます。
文頭の分詞構文
分詞構文は多くの場合、文頭に置かれます。
分詞構文を用いる場合は、主節と従属節を区別するために「,(カンマ)」で区切ることが多いですが、入っていない場合もあります。
【例文】
Reading his papers, I found many misprints.
彼の書類を読んでいるとき、誤植を沢山見つけた。
Reading his papers I found many misprints.
彼の書類を読んでいるとき、誤植を沢山見つけた。
どちらも全く同じ分詞構文の文章ですが、カンマがない方がやや判別が難しくなりますね。
文中の分詞構文
稀に分詞構文は文中に置かれることがあります。
その場合もその他の要素と区別をするために、前後に「,(カンマ)」を入れるのが一般的です。
【例文】
The perpetrators, seeing the police, they ran away at once.
犯人は警察を見て、一目散に逃げ出した。
文末の分詞構文
また、分詞構文は文末に置かれることもあり、「,(カンマ)」を入れることがあるのも同様です。
【例文】
My mother is cooking dinner,humming her favorite tune.
母は好きな曲を口ずさみながら、夕食を作っている。
文末に置かれる場合は「そして~する」や「~しながら」のような連続した動作や同時進行で訳すことが多い表現です。
分詞構文における否定語の位置
否定の意味を持つ分詞構文を作る場合は、「not」を用います。
【例文】
Not knowing what to do, I stood there.
何をしたらいいか分からず、私はその場に立ち尽くしていた。
もっと強い否定の意味を表す場合には「never」を用いて分詞構文を作ることができます。
【例文】
Never smoking again, your health will be maintained.
二度とタバコを吸わなければ、あなたの健康は維持できます。
接続詞+分詞構文
分詞構文を使った文章では、時にその意味が曖昧になることがあります。
その意味が曖昧になることを回避するために、分詞の前に接続詞を置いて意味を明確にして表現することがあります。
【例文】
While staying in England, I learned a lot of English.
イギリスに滞在している間、私はたくさんの英語を学びました。
If not raining, the plants will die.
雨が降らなければ、植物は枯れてしまいます。
受動態の分詞構文
受動態においても分詞構文は使用されます。
一般的に受動態の文法は
【受動態の分法】
主語 + be動詞 + 過去分詞
です。
まず通常の受動態の文章を見ていきましょう。
【例文】
When it is seen from a distance, the rock looks like a giant.
遠くから見ると、まるで巨人のような岩です。
これを分詞構文にすると、
【例文】
Being seen from a distance, the rock looks like a giant.
となります。
分詞構文の受動態の文法は、
【分詞構文の受動態の分法】
Being + 過去分詞~
で表現します。
そして分詞構文の受動態の場合、「Being」はしばしば省略され、
【例文】
Seen from a distance, the rock looks like a giant.
となります。
独立分詞構文
分詞構文は主節と従属節の主語が一致していましたが、その主語が同じではない場合でも分詞を使って表現をすることがあり、それを独立分詞構文と言います。
独立分詞構文の場合、主語が異なるので分詞のまとまりにおける主語は省略されません。
【例文】
Weather permitting, we will go on a picnic tomorrow.
天候が良ければ、明日はピクニックに行きます。
まとめ
分詞構文の基本について解説をしていきました。
分詞構文には様々な意味があり、その判別が難しいように感じられますが、まずは分詞のまとまりにおいて、なんとなく「動詞+~して、」と訳してみるようにしましょう。
「走って~」「見て~」の後に主節を続けてみて、文脈でだいたいどの意味であるかの見当をつけるくらいで問題ありません。
分詞構文において意味のパターンはありますが、厳密にそれを分別せずに意味のゆらぎが起きることもあります。
あまり意味の分別に悩むことなく、「こういう意味だろう」くらいの判断でこの文法に慣れると良いでしょう。






