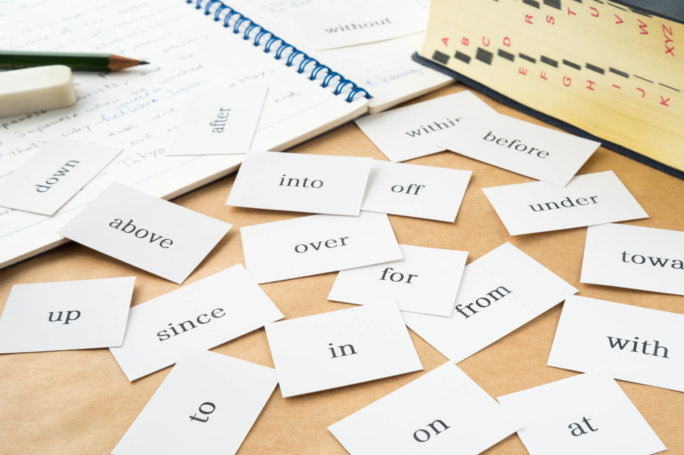混同しやすい英熟語「used to V」と「be used to Ving」を徹底解説!
「used to + 動詞の原形」は、過去に習慣的に行っていた行動や、過去に存在していた状態を表し、現在はそうではないことを示唆する表現です 。この表現は、常に過去の事柄にのみ言及し、現在の習慣や状態には使用されません 。例えば、「以前はサッカーをしていたが、今はしていない」といった過去の習慣や、「以前はここにカフェがあったが、今はもうない」といった過去の状態を表現する際に用いられます。

この表現の背後にある文法的な機能は、一般的な助動詞に類似しています 。助動詞は通常、動詞の原形を伴い、時制変化せず、疑問文や否定文では「do/did」を伴うという特徴があります。この助動詞的な性質を理解することは、「used to + 動詞の原形」という構造がなぜ固定されているのか、また「be動詞」を伴わないのかを論理的に把握する上で極めて重要です。この理解は、他の助動詞(can, shouldなど)との比較を通じて、その構造的な固定性をより深く認識させ、誤用を防ぐための強力な基盤となります。
肯定文・否定文・疑問文の構造と例文
「used to + 動詞の原形」を用いた文の構造は以下の通りです。
- 肯定文: 主語 + used to + 動詞の原形
- 【例文】We used to live in a big city.
私たちは以前、大都市に住んでいました。
- 【例文】We used to live in a big city.
- 否定文: 最も一般的な形は 主語 + didn’t use to + 動詞の原形 です 。
- 【例文】He didn’t use to like vegetables.
彼は以前、野菜が好きではありませんでした。
非常にフォーマルな文体では 主語 + used not to + 動詞の原形 も可能です 。
- 【例文】She used not to live as poorly as she does now.
彼女は以前、今ほど貧しく暮らしていませんでした。
- 【例文】He didn’t use to like vegetables.
- 疑問文: 最も一般的な形は Did + 主語 + use to + 動詞の原形? です 。
- 【例文】Did you use to work with Kevin?
あなたは以前ケビンと一緒に働いていましたか?
- 【例文】Did you use to work with Kevin?
よくある間違い:「d」の有無に注意!
「used to」の誤用で最も頻繁に見られるのは、スペリングに関するものです。話し言葉では「used to」の「d」と「to」の「t」の音が結合して聞こえにくくなるため、多くの学習者が「use to」と誤って書いてしまいます 。しかし、肯定文では必ず used to と表記する必要があります 。
- 【例文】誤:I use to live in London.
- 【例文】正:I used to live in London.
一方で、否定文や疑問文では「did」が過去を表す助動詞として使用されるため、その後に続く「use to」は原形に戻ります。したがって、didn’t used to や Did you used to? は文法的に誤りです 。
- 【例文】誤:She didn’t used to drive so fast.
- 【例文】正:She didn’t use to drive so fast.
- 【例文】誤:Did you used to climb trees?
- 【例文】正:Did you use to climb trees?
これらのスペリングの誤りは、発音時の音の連結が書記に影響を与えるという音声学的な要因から生じます。学習者が「なぜこの間違いが起こるのか」を理解することで、単にルールを暗記するよりも、より深く記憶に定着させ、間違いを減らすことができます。これは、英語のように発音とスペリングが必ずしも一致しない言語において、音と文字の関係性の複雑さを認識することの重要性を示しています。
また、方言による違いも存在します。アメリカ英語では「didn’t use to」が一般的ですが、イギリス英語では「used to not」も許容されます 。さらに、一部のイギリス英語では「did used to」も使われることがありますが、これは試験などでは避けるべき形式とされています 。
「would」との違い
「used to」と「would」はどちらも過去の習慣的な行動を表すことができますが、重要な違いがあります 。
- 「used to」: 過去の習慣的な行動と状態の両方に使えます。
- 【例文】We used to live in Manchester.
(状態) - 【例文】He used to play football.
(習慣的な行動)
- 【例文】We used to live in Manchester.
- 「would」: 過去の習慣的な行動にのみ使え、状態には使えません 。
- 【例文】誤:We would live in Manchester.
- 【例文】正:When we were kids, we would invent amazing games.
(習慣的な行動)
両方を併用する場合、「used to」が先にきて状況を設定し、「would」がその後の具体的な行動を説明することが多いです 。
2. 「be used to + V-ing/名詞」の理解:慣れている状態を表す
「be used to + V-ing/名詞」は、何かに慣れている、順応している状態を表す表現です 。これは、その事柄がもはや難しくも、新しくも、奇妙でもないと感じることを意味します 。この表現は、過去、現在、未来のいずれの時制でも使用可能であり、その際の「be動詞」は時制に合わせて変化します 。このフレーズにおける「used to」は、動詞ではなく形容詞として機能します 。
肯定文・否定文・疑問文の構造と例文
「be used to + V-ing/名詞」を用いた文の構造は以下の通りです。
- 肯定文: 主語 + be動詞 + used to + V-ing/名詞
- 【例文】I am used to waking up early.
私は早起きに慣れています。 - 【例文】She is used to the noise of the city.
彼女は都会の騒音に慣れています。 - 【例文】He was used to traveling for work.
彼は仕事で旅行することに慣れていました。
- 【例文】I am used to waking up early.
- 否定文: 主語 + be動詞 + not + used to + V-ing/名詞
- 【例文】She is not used to cold weather.
彼女は寒い天候に慣れていません。
- 【例文】She is not used to cold weather.
- 疑問文: Be動詞 + 主語 + used to + V-ing/名詞?
- 【例文】Are you used to driving on the left?
あなたは左側通行に慣れていますか?
- 【例文】Are you used to driving on the left?
なぜ「V-ing」形を使うのか?
「be used to」の後に動名詞(-ing形)が続く理由は、多くの学習者がつまずくポイントです。この表現における「to」は、不定詞の「to」ではなく、前置詞としての「to」だからです 。英語の文法規則では、前置詞の後に動詞が続く場合、必ず動名詞(-ing形)を使用するというルールがあります。これが、「be used to」の後に動名詞が来る根本的な理由です 。
例えば、「I’m good at swimming.」という文では、前置詞「at」の後に動名詞「swimming」が来ています。同様に、「I’m used to working late.」では、前置詞「to」の後に動名詞「working」が来ています。この前置詞としての「to」の役割を理解することは、多くの学習者が「to + 動詞の原形」という不定詞のパターンに慣れているために、「be used to V」と誤用する根本的な原因を解明します。この認識は、単に「V-ingを使う」というルールを覚えるのではなく、その背後にある文法的な理由を理解させることで、より深い学習と定着を促します。これにより、学習者は「to」の多様な文法的役割(不定詞マーカー、前置詞)を認識し、他の前置詞句における動名詞の使用(例: look forward to Ving, object to Ving)との関連性も見出すことができ、文法知識の体系化に貢献します。
様々な時制での使い方
「be used to」は「be動詞」を時制に合わせて変化させることで、過去、現在、未来の慣れを表すことができます 。
- 【例文】現在: I am used to the cold.
私は寒さに慣れている。 - 【例文】過去: When I lived there, I was used to the noise.
そこに住んでいた頃、私はその騒音に慣れていました。 - 【例文】未来: You will soon be used to living alone.
あなたはすぐに一人暮らしに慣れるでしょう。
3. 「get used to + V-ing/名詞」の理解:慣れる過程を表す
「get used to + V-ing/名詞」は、何かに慣れる過程、つまり順応していく変化を表す表現です 。これは「be used to」が表す「慣れている状態」とは異なり、まだ慣れていない状態から慣れた状態へと移行する動的なプロセスを示します 。例えば、新しい環境や習慣に順応していく途上にあることを表現する際に用いられます。よりフォーマルな表現として「become used to」も使われます 。
「慣れ」という概念を完全に理解するためには、「状態」(be used to)だけでなく、「その状態に至る過程」(get used to)も不可欠です 。この区別は、「state not a process」と「process of becoming familiar」という明確な違いとして説明されます 。この区別を理解することは、学習者がより細やかな意味合いを表現できるようになるための、高度な語彙選択能力に繋がります。単に文法構造を覚えるだけでなく、それぞれの表現が持つ意味のニュアンス(静的か動的か)を理解することの重要性が強調され、これにより、学習者は状況に応じて最も適切な表現を選ぶことができるようになり、より自然な英語表現が可能になります。
構造と例文
「get used to」も「be used to」と同様に、「get動詞」を時制に合わせて変化させ、その後に動名詞または名詞が続きます 。
- 【例文】現在: I’m slowly getting used to the weather here.
私はここの天候に徐々に慣れてきています。 - 【例文】過去: I hated this haircut at first, but I got used to it.
最初は嫌いだったこの髪型も、慣れてきました。 - 【例文】未来: You will get used to living alone soon.
あなたはすぐに一人暮らしに慣れるでしょう。
進行形は、慣れるプロセスが現在進行中であることを強調する際によく使われます 。
- 【例文】They are still getting used to the traffic in this city.
彼らはまだこの街の交通に慣れている途中です。
4. 徹底比較!「used to V」と「be used to Ving」の決定的な違い
これらの表現の混同を避けるためには、その意味、文法構造、時制、そして「to」の役割を明確に区別することが不可欠です。以下の比較表で、それぞれの違いを一目で理解することができます。
この表は、学習者が「混同しやすい」という問題に対処するために非常に有効です。テキストで説明するだけでは情報が散漫になりがちですが、表形式は異なる概念を横並びで比較できるため、視覚的に違いを際立たせ、情報の整理と理解を劇的に促進します。意味、品詞、構造、時制、否定形、疑問形、そして「to」の役割といった多角的な視点から比較することで、学習者が抱く可能性のあるあらゆる疑問に一度に答えることが可能です。特に「to」の役割の違いは、なぜ動詞の形が変わるのかという根本的な疑問を解決する鍵となります。複雑な文法事項を一度に比較できるため、学習者は各表現の独自性を素早く把握し、記憶に定着させやすくなります。これは、試験対策や日常会話での即座の判断に役立ちます。
混同しやすい英熟語:徹底比較表
| 項目 | used to + 動詞の原形 | be used to + V-ing/名詞 | get used to + V-ing/名詞 |
|---|---|---|---|
| 意味 | 過去の習慣や状態 (現在は違う) | 何かに慣れている状態 | 何かに慣れる過程 |
| 品詞/機能 | 助動詞的 (modal-like verb) | 形容詞句 (adjectival phrase) | 形容詞句 (adjectival phrase) |
| 構造 | 主語 + used to + 動詞の原形 | 主語 + be動詞 + used to + V-ing/名詞 | 主語 + get動詞 + used to + V-ing/名詞 |
| 時制 | 常に過去 | 過去・現在・未来 | 過去・現在・未来 |
| 「to」の役割 | 不定詞の to (infinitive marker) | 前置詞の to (preposition) | 前置詞の to (preposition) |
| 否定文 | didn’t use to / used not to | be動詞 not used to | not get used to |
| 疑問文 | Did + 主語 + use to…? | Be動詞 + 主語 + used to…? | Get動詞 + 主語 + used to…? |
| 例文 | I used to live there. | I am used to living there. | I am getting used to living there. |
5. 英語学習者が陥りやすい共通の落とし穴と対策
これまでに解説した内容を踏まえ、特に注意すべき共通の誤用とその対策をまとめます。これらの誤用の根本原因は、単なる記憶違いではなく、それぞれの表現が持つ異なる文法的な機能(助動詞的機能と形容詞句、不定詞マーカーと前置詞)を理解していないことに起因します。この機能の混同が根本原因であることを認識することは、表面的なルールだけでなく、その背後にある深い文法概念を理解することが、長期的な誤用防止に繋がるという学習効果の因果関係を示唆しています。この認識は、学習指導において、単に「こう使う」と教えるだけでなく、「なぜそう使うのか」という文法的根拠を説明することの重要性を強調します。これにより、学習者はより深く、そして柔軟に文法を応用できるようになります。
「used to」と「be used to」の混同
最も一般的な間違いは、過去の習慣を話す際に「be動詞」を「used to」の前に置いてしまうことです 。これは「be used to」が「慣れている」という意味を持つため、混同が生じやすいです。
- 【例文】誤:I am used to go to that park.
(過去の習慣を言いたい場合) - 【例文】正:I used to go to that park.
対策: 「used to + 動詞の原形」は「過去の習慣」を表す固定表現であり、「be動詞」とは組み合わせないことを徹底的に覚えましょう。
「to」の後に動詞の原形か-ing形か
「used to + 動詞の原形」では「to」は不定詞のマーカーなので動詞の原形が続きます。しかし、「be used to + V-ing/名詞」や「get used to + V-ing/名詞」では「to」は前置詞なので動名詞(-ing形)や名詞が続きます 。この違いを混同すると、意味が全く通じなくなります。
- 【例文】誤:She is used to live in a big city.
- 【例文】正:She is used to living in a big city.
対策: 「be used to」や「get used to」を見たら、その後の「to」は前置詞だと意識し、動名詞または名詞が続くことを確認する習慣をつけましょう。これは「to」の文法的な役割(不定詞 vs 前置詞)を理解することが、これらの混同を解消する鍵となります。
「used to」のスペルミス(特に否定文・疑問文)
肯定文で「-d」を忘れる(use to → used to) 、または否定文や疑問文で「-d」を加えてしまう(didn’t used to → didn’t use to, Did you used to? → Did you use to?) といったスペルミスは非常に多いです。
対策: 「did/didn’t」が使われる文では「use to」の形に、それ以外では「used to」の形になるというルールを徹底的に練習しましょう。発音に惑わされないことが重要です。
実践的な助言
これらの誤用を避けるためには、意識的な学習と実践が不可欠です。
- 例文を音読する: 各表現の例文を繰り返し声に出して読むことで、口と耳で正しい形を覚え、自然と身につけることができます。
- 自分の言葉で例文を作る: 自分の経験や日常に関連する例文を積極的に作成し、アウトプットを通じて定着を図りましょう。
- 比較表を常に参照する: 迷ったときは、本記事の比較表をすぐに参照し、違いを再確認する習慣をつけましょう。
まとめ:これで完璧!「used to」マスターへの道
本記事では、英語学習者にとって特に混同しやすい「used to + 動詞の原形」「be used to + V-ing/名詞」「get used to + V-ing/名詞」の三つの表現について、その意味、構造、そして正しい使い方を詳細に解説しました。これらの表現をマスターすることは、英語の過去の習慣や現在の慣れを正確に伝える上で不可欠です。
主要なポイントは以下の通りです。
- used to + 動詞の原形: 過去の習慣や状態を表し、現在はそうではないことを意味します。常に過去形であり、「did」を伴う否定文・疑問文では「use to」となります。
- be used to + V-ing/名詞: 何かに慣れている「状態」を表します。「be動詞」は時制に応じて変化し、「to」は前置詞であるため、その後には動名詞または名詞が続きます。
- get used to + V-ing/名詞: 何かに慣れる「過程」を表します。「get動詞」は時制に応じて変化し、「to」は前置詞であるため、その後には動名詞または名詞が続きます。
- 最も一般的な間違いは、「used to」と「be used to」の混同、特に「be動詞」の有無と「to」の後の動詞の形です。
- 発音とスペリングの乖離、そして「to」の文法的な役割(不定詞 vs 前置詞)の理解が、これらの混同を解消する鍵となります。
文法は一度学んだだけでは完璧にはなりません。日常生活の中でこれらの表現を意識的に使い、間違いを恐れずに練習を重ねることが重要です。映画やドラマ、英語のニュースなどでこれらの表現がどのように使われているか注意深く観察し、実際のコミュニケーションの中で活かしていきましょう。継続的な学習と実践を通じて、これらの表現を自信を持って使いこなせるようになるでしょう。